日常生活で適性検査対策
「勉強しなさい!」と言わなくても、日常の中で自然に思考力を育てる方法があります。
今回は、東京都立三鷹中等教育学校の2012年(平成24年度)の過去問を例に、家庭でできる学習の工夫を紹介します。
三鷹中等の過去問は「チョコレート」がテーマ
この問題では、チョコレート製品の成分表示から「チョコレート」「準チョコレート」などの分類を考えさせる設問が出題されました。
たかおくんとみつこさんは、チョコレート製品について調べることにしました。
たかお:チョコレート製品の箱の表示を見てみよう。原材料名や内容量が書いてあるね。この板 チョコレートは種類別名称が「チョコレート」となっているよ。
みつこ:このナッツチョコレート(図1)は、種類別名称が「準チョコレート菓子」となっているわ。何が違うのかしら。
先生:チョコレート製品は、カカオ分の割容や、チョコレート製品にふくまれる生地の割合によって 4種類に分類することができます。(表1)
表1 チョコレートの分類表
(日本チョコレート・ココア協会の資料から作成)
たかお:「カカオ分」や「生地」って何ですか。
先生:カカオ分とはチョコレートの原料であるカカオ豆にふくまれる成分のことで、生地とはカカオ分と砂糖などがふくまれている部分です。
たかお:この板チョコレートは,「チョコレート」に分類されているから,カカオ分の割合は生地の重さの35%以上なのですね。「チョコレート」と「チョコレート菓子」は、どのように違うのですか。
2012(平成24)年度東京都立三鷹中等教育学校検査Ⅰ出題より一部抜粋
たかお:チョコレート製品の箱の表示を見てみよう。原材料名や内容量が書いてあるね。この板 チョコレートは種類別名称が「チョコレート」となっているよ。
みつこ:このナッツチョコレート(図1)は、種類別名称が「準チョコレート菓子」となっているわ。何が違うのかしら。
先生:チョコレート製品は、カカオ分の割容や、チョコレート製品にふくまれる生地の割合によって 4種類に分類することができます。(表1)
表1 チョコレートの分類表
| 種類別名称 | カカオ分の割合 | 製品に含まれる生地の割合 |
チョコレート | 生地の重さの35%以上 | 全体の重さの60%以上 |
| チョコレート菓子 | 生地の重さの35%以上 | 全体の重さの60%未満 |
| 準チョコレート | 生地の重さの35%未満 | 全体の重さの60%以上 |
| 準チョコレート菓子 | 生地の重さの35%未満 | 全体の重さの60%未満 |
(日本チョコレート・ココア協会の資料から作成)
たかお:「カカオ分」や「生地」って何ですか。
先生:カカオ分とはチョコレートの原料であるカカオ豆にふくまれる成分のことで、生地とはカカオ分と砂糖などがふくまれている部分です。
たかお:この板チョコレートは,「チョコレート」に分類されているから,カカオ分の割合は生地の重さの35%以上なのですね。「チョコレート」と「チョコレート菓子」は、どのように違うのですか。
2012(平成24)年度東京都立三鷹中等教育学校検査Ⅰ出題より一部抜粋
チョコの成分の違いは、普段意識していませんが、改めて見るとなるほど、という気づきもありますね。
実際の問題はさらにチョコを使用した製品についても言及していますので、気になる方はぜひ過去問をチェックされてみてくださいね。
実際の問題はさらにチョコを使用した製品についても言及していますので、気になる方はぜひ過去問をチェックされてみてくださいね。
適性検査で求められる力
- 表やデータから情報を正確に読み取る力
- 比較して判断し、理由を説明する力
- 数値をもとに割合や計算を行う力
過去問から学ぶポイント
- 情報整理:表の数値を読み取り、何が重要かを見抜く練習が必要
- 割合計算:例えば「カカオ20gは生地の何%?」と考え、割合の計算に慣れておくこと
- 違いを言葉で説明する:「なぜこの製品はこの分類?」「このチョコはカカオが多いから苦いね」など、自分の言葉で説明する力をつける
家庭でできる取り組み例
- 日常の中で:買い物中やおやつの時間に「このチョコ、カカオ分は何%?」「どうしてこれは『チョコレート菓子』なの?」と話してみる
- 食べながら学ぶ:チョコの味や食感の違いを楽しみながら「カカオ分が多いとどんな味?」「生地の割合が多いとどう感じる?」と、体験を通じて割合の違いを感じ取る
- お菓子作りで:材料を量りながら「全体の〇%は?」と一緒に考え、割合の感覚を養う
さらに深める学習対策
- 型の工夫で思考力を養う:型の形でチョコの冷えやすさが変わる理由を、図を見ながら考えてみましょう。クッキー型や製氷皿を使い、「どの形が早く固まる?」と実験し、「なぜこの形は冷えやすい?」と問いかけることで思考力を育てます。
親子で「なんでだろう?」を大切に
机に向かうだけが勉強ではありません。
日常の中で「これってどうして?」と考える時間を作るだけで、適性検査で求められる思考力・判断力が自然と身につきます。
今日のおやつタイムから、ぜひ始めてみてください!
日常の中で「これってどうして?」と考える時間を作るだけで、適性検査で求められる思考力・判断力が自然と身につきます。
今日のおやつタイムから、ぜひ始めてみてください!
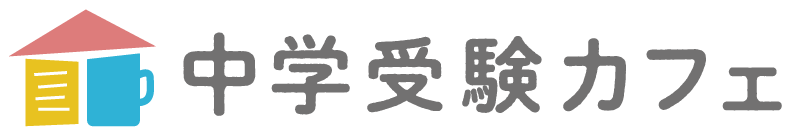




20191008-375x281.jpg)